 |
 |
|
Chapter1 現代の魔法使い |
| Chapter1-1 口は災いの素 |
 |
「君はマーリンにでも成ったつもりかね」 課長室に入るなり、そんなことを言われて。ベンジャミン・ハロルド=シェリンガムは、ただ一言、いいえとだけ答えた。 目の前のマホガニーのデスクに座っているハゲ頭の男は、ランドルフ=カヴェンディッシュ警視正。ロンドン首都警察──通称、スコットランドヤードの重犯罪対策局・殺人捜査部・西部地区課長サマだ。言葉には気をつけないといけない。ベンジャミンは笑いをかみ殺した神妙な表情のまま。黙って立っている。 「シェリンガム警視、私はこれでも君のことをずいぶん高く買っているつもりだ」 低く抑えた警視正の声には、怒気が含まれていた。 「君はオックスフォード出の秀才で、家柄も素晴らしいし、あのプレスコット下院議員は君の叔父だと聞いている。私が警視になったのは43才の時だが、君は38才でもう警視だ。実際、私の補佐役としてよく働いてくれているし、手際の良さにはいつも舌を巻く限りだ。しかしな」 一気に喋ってから、ギラリとした視線をベンジャミンに投げ打つ。 「今回ばかりは、君の考えが理解できない。一体どうして、ああいったことをしでかしてくれたのかね? 君はBBCの連中に借りでもあるのか」 「いえ、ありません。深夜にやっている“男のクッキング24時”は好きですがね」 ニヤと一瞬だけ笑みを見せて、ベンジャミンは相手が反応する前に言葉を続けた。 「私も、警視正と同じで、メディアの連中は大嫌いですよ。ヘドが出ますね。しかし、BBCはあれでも国営放送ですから、どこからか我々の情報力操作の及ばないところから、マハムード=アサディがあの場所に現れることを掴んだんでしょうな」 「他人事のように言うな!」 ドンッ、とカヴェンディッシュ警視正はデスクを叩いた。 「奴をなぜ、逃がしたんだ!? 理由を言え」 だが、ベンジャミンは冷たい視線を相手に据えただけだった。栗色の髪は、ラフにセットされており、サヴィル・ロウ ※ (紳士服スーツの老舗がズラリと並ぶ英国紳士ファッションの聖地。) の老舗テーラー、ギーブス&ホークスのスーツを着ているにも関わらず、シャツの第一ボタンを開けネクタイを緩めている。一見だらしないように見えるのだが、それが妙にサマになっている。不思議な雰囲気のする男だった。 「逃がしたつもりはありません。彼が消えたのです。我々の前から、フッ、とね」 彼は堪えきれずに、クスッと笑う。 「土曜日、昼間のトラファルガー・スクエアがどれほど人で込み合うか、警視正はご存知ないようだ。まあ、要するに私が現場への指示をミスしたわけですから、処罰・処断、如何様にもなさっていただいて結構」 「シェリンガム、俺の立場も考えてくれ!」 とうとうカヴェンディッシュ警視正は、椅子を蹴倒して立ち上がっていた。 「我々が逮捕するはずだった容疑者が、ハイドパークの市民論壇場 ※ (ハイドパークという大きな公園がありまして。その角に市民が勝手に喋っていい「公開シャベリ場」があるのです。) スピーカーズコーナーに突然現れて、自分の無実を訴えたんだぞ。しかもそれをBBCが生中継だ! 悪いジョークにも程があるだろうが!」 ひょいと肩をすくめるベンジャミン。カヴェンディッシュ警視正は、それを見なかったことにして、椅子を戻し荒く息をしながら腰掛けた。 「マハムード=アサディの無実の訴えに、ロンドン市民は心を動かされてしまった。これで奴を逮捕することが難しくなった。捜査もまた一からやり直しだ」 「いいんじゃないですか。捜査をやり直すことに、私は賛成です」 しかし淡々と、ベンジャミンは言った。 「アサディに関する調査報告書に目を通しました。今のところ物的証拠が少な過ぎます。同じ状況で逮捕・起訴された人間は過去には一人も居ないはずです。過去の類似事件と違う点は、アサディがイラン出身のイスラム系移民であるということだけです。これは宗教・人種上の差別には当たりませんか」 「ま、待て、落ち着け、シェリンガム」 突然、部下が言い出した糾弾に、警視正は目に見えるほど狼狽した。ここは個室で、ほかには誰も居ないというのに周囲にキョトキョトと目線を走らせ始める。 「アサディを逮捕しろと言ってきたのは、MI5(国防情報局保安部) ※ (国内方面のテロ対策をする情報局。ジェームズ・ボンドが所属してるのはMI6で、あれは外交方面の活動をします。だからボンドは海外に行くのね) で、報告書も連中が作ったわけで……」 「連中の言いなりになる必要がありますか、我々は警察ですよ。しかもMI5からテロ対策部ではなく、この殺人捜査部にお鉢が回ってきたということは、アサディを別件逮捕して取り調べるつもりだったんでしょうな。それぐらいのこと、貴方でもお分かりでしょう?」 カヴェンディッシュ警視正は、ひるんだように上体を反らせた。 「それに──」 たたみかけるように、ベンジャミンは続けた。 「私のことをマーリンと呼ぶのはやめた方がよろしいかと。私は魔法使いではありませんし、もし私がマーリンだとしたら……」 |
| Chapter1-2 超常犯罪調査部、略してUCB |
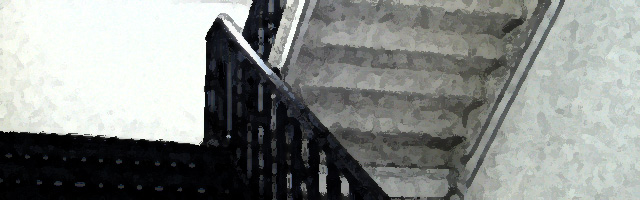 |
そんなわけで、三日後の夕刻。 ベンジャミン・ハロルド=シェリンガムは、かったるい、ウザいなどと悪態をつきながら、両手でダンボールを抱えて階段を降りている。スコットランドヤードのビルの中に、こんな場所が存在したのかと驚くほど薄暗い陰気な場所だ。階段の終点から少し行ったところの突き当たりに、古ぼけたドアがあった。張り出した札にあるのは── 『超常犯罪調査部アンノウン・クライム・ブランチ(UCB)』 ドアの前に立ったベンジャミン。両手がふさがっているため、肩でドアをノックし、中にいる人間にドアを開けてもらおうとしたのだが、彼は動きを止めた。中から女性二人の話し声が聞こえてきたからだ。 「……マジで? それヤバくない?」 「ヤバイわよ。それでもシェリンガムさんは、動じずに、ソファに座ったままタバコふかしてただけだったらしいわ」 「だって目の前に殺人鬼でしょ?」 「そうよ、殺人鬼よ。ドラッグキメてる殺人鬼よ」 「ウッソ、殺されちゃうじゃん」 「部下を信じてたらしいわよ。実際、そのすぐ後に西課の連中がカフェに踏み込んで、犯人を射殺したんだって。それでシェリンガムさんは、殺人犯の死体に向かって、“ヤードを恨むのは結構だが、他人を殺すのは罪だ”とか言ったんですって」 「カァッコィィ……」 「ヤードの中で、最もラフにギーブス&ホークスを着こなす男とも呼ばれてるらしいわよ」 「なんで、そんなスゴイ人がこんな部に回されちゃうわけ?」 「それよ、それ。マーリン発言よ」 「何それ」 「カヴェンディッシュ西課長にね、“君はマーリンか?”って言われたんだって。例のイラン人のアサディ生中継事件の件でね。……そしたら、シェリンガムさん。自分がマーリンだったら、貴方はアーサー王になるわけで、貴方にアーサー王は無理だとかなんとか言ったんだって。それで西課長、大・激・怒よ」 「ギャハハ、けっさくー」 ドンドン。 「君たち、ちょっとドアを開けてくれないか」 中から聞こえてきた女性たちの笑い声がピタリとやんだ。 外れて落ちてしまいそうなドアノブがキュル、と回り、ドアが開く。そこに立っていたのは、いずれも20代ぐらいの赤毛とブロンドの女性二人だ。 女性二人は呆けたように、ベンジャミンの顔を見上げる。 「シェリンガムだ。話は聞いてる?」 「は、はい」 「俺の机はどこ?」 「こちらです」 赤毛の方が身を引いて、部屋の奥に鎮座した味気ないステンレスのデスクを手で指し示した。日光が射さない地下のこの部屋の中は、昼間だというのに薄暗い蛍光灯が灯っているだけで、10個ほど並んだデスクには人影が一つもない。 どうも女性二人以外は、捜査か外回りに出かけているようだ。それにしても……。聞き及んではいたものの、人数の少なさに改めて驚くベンジャミン。こんな少ない人数で成立する“部”があるのか、と。 自分の新たなデスクにダンボールを下ろし、一息つこうとして、ベンジャミンは気配にサッと振り返る。すると女二人が顔を赤らめ、それぞれそっぽを向いたところだった。 「君たち、ちょっと」 ベンジャミンが呼ぶと、彼女たちは慌てたように彼の目の前に駆けつけ、ヘナッとサマにならない敬礼をした。 「ベンジャミン=シェリンガム警視だ。今日からこの超常犯罪調査部を預かることになった。よろしく」 何で俺から名乗ってるんだろ、などと思いながらもベンジャミン。デスクに手を付きながら言う。 「ヴィヴィアン=コーヴェイです!」 「シシー=デューモントです!」 女二人は競うようにして名乗った。まだ新人ですとか、この4月に入所したばかりですとか、まだ現場に出たことがありませんとか、電話番してるだけですとか、シェリンガムさんの下で働けて光栄です、とか、彼女たちはマシンガンのように口々に喋り狂った。 「ああ、分かった分かった。この部のことは明日にでも、ほかのメンバーも交えてゆっくり聞くから」 と、ベンジャミンはなだめるようにそう言うと、赤毛の女の方に向かって、 「ところで、シシー。過去にこの部で扱った事件のことを掴みたいんだが、資料は……」 「わたしはヴィヴィアンです。ヴィヴって呼んでくださって構いませんです!」 「あ、ごめん」 赤毛の方がヴィヴィアンだったか、と思ったら脇からブロンドのシシーが大声を張り上げた。 「資料の方は、わたしシシーの方が管理してます! 何でも聞いてください」 「何よ、アンタいつもインターネットして遊んでるだけじゃないの!」 「違うわ、あれは調査してんのよ!」 「まあまあ」 突然、噛み付くような言い争いを始める二人。ベンジャミンは、何でなだめてるんだろ、などと思いながら彼女たちの肩にポンと手を置く。 「資料の件も明日でいいや。悪いんだけど、そのダンボールの中の荷物、俺のデスクの中にテキトーにぶっ込んどいてくれる? ……ああ、一番上に乗ってる薬ビンがあるだろ。それは持って帰るからこっちに寄こして」 そう言いながら胸ポケットから携帯電話を取り出す。 女二人は、伝統的英国紳士風のルックスをした、いかにも上流階級アッパークラスの人間に見えるベンジャミンの口から、思いも寄らないフランクな言葉が飛び出てきたことに驚いて、またポカンと口を開けて彼を見つめている。 しかし、そうとは知らないベンジャミンは左腕に嵌めたタグホイヤーで時刻を確認すると、そろそろ行ってやるか、と呟いた。電話をかけようと携帯電話の画面を見つめていると、また女たちの視線を感じた。ブロンドのシシーの方がおずおずと薬ビンを彼に差し出している。 「ああ、ありがとう。シシー」 ベンジャミンは薬ビンをスーツのポケットに入れた。先日、医者にγ−GDP値※が高過ぎるがら、とにかくこれを飲んで肝機能を治せと渡されたものだ。 「シシー。それにヴィヴ。今日はちょっと行くところがあるから、これで失礼するよ。明日はちゃんと定時に来るから」 電話をかけながら部屋を出ようとして、ベンジャミンはふと女二人を振り返った。彼女たちは、なんと声をかけてよいものやらといった感じでモジモジしながら自分を見ている。 「あのさ」 ベンジャミンは携帯電話を持った手を下げ、彼女たちに微笑みかけた。 「“君はマーリンか”って言われたアレな」 ヴィヴィアンとシシーは噂話を聞かれたことを知り、驚きそして恥じたような苦笑いを浮かべてみせる。 「──君たちが言ってた話で大体合ってるが、正確には、俺はこう言ったんだ。“自分がマーリンなら、貴方はアーサー王になるわけで。貴方は部下9人と円卓を囲めますか? 円卓を囲んだら、‘お前たちは俺の言うことを聞いてりゃいいんだ’なんて言えなくなりますよ”ってな ※ (アーサー王の円卓は、王も臣下もフラットな立場で話し合うために用意されたもの。円卓であるため、上座や下座がない) 」 プッと吹き出すように笑う女二人。 「“それでしたら、私はマーリンでなく、フーディーニ ※ (ハリー・フーディーニ。奇術師。心霊術などのインチキを見抜くことに熱心だったといわれている。ドラマ「TRICK」でも彼の名前、出てきますよね?) で結構。奇術師ながらも同業者のイカサマを見破って暴いてみせますから”って最後締めくくったんだ。けど、あのカヴェンディッシュ警視正どのは、センス・オブ・ユーモアを解さない男だったらしく。そう、君たちの言う通り大激怒さ。顔を真っ赤にしてさ、見ものだったぜ?」 二人は、若い女らしくけたたましく笑いだした。腹を抱えて大笑いしている。英国の淑女はたぶん絶滅したのだろう、そう思いながらも、ベンジャミンは新しい異動先を後にした。 |
|
■■■ |